
NHK朝ドラ『らんまん』は、毎週の副題(サブタイトル)に草花の名が設定されています。
ここでは、その草花の特徴や花言葉、そして、その花にまつわるエピソードから、ドラマとの関係をひも解いて行きます。
【らんまん図鑑】1週バイカオウレン
らんまん1週の花の名【バイカオウレン】

らんまん1週バイカオウレン|特徴
らんまん1週の『バイカオウレン(梅花黄蓮)』(学名:Coptis quinquefolia)は、本州の福島より南と四国にも分布。
明るい半日陰と柔らかく湿った土壌を好むキンポウゲ科オウレン属の常緑多年草です。
高さは3~10cmほどのかわいらしいサイズです。
縁に切れ込みのある5枚に分かれた小さな葉と、早春の2月から3月ごろに咲く直径1.5cmぐらいの真っ白な花が印象的です。
花は梅のような形で、小さな5枚の白い花びらと中心から飛び出しためしべとおしべに特徴があります。
ただしこの「花びら」は、実はがく片で、本物の花びらはその内側に存在する、スプーンのような黄色い部分です。
らんまん1週バイカオウレン|花言葉

バイカオウレンの花言葉「2度目の恋」「情熱」「魅力」「忍ぶ恋」など。
清楚な印象にもかかわらず、激しい思いを秘めた言葉が並んでいます。
なぜ清楚な花にこのような花言葉が付いたのでしょうか。
太陽の下で輝くように咲く花ではないので、一見清らかであってもどこか陰を感じる人も多く、このような意味深長な花言葉になったと言われています。
らんまん1週バイカオウレン|エピソード

バイカオウレン(梅花黄連)は、【らんまん】のモデルとなった植物学者・牧野富太郎博士が特に好きだった花として有名です。
しかし、その理由は「故郷(高知)の裏山に群生していたから」というもので、とても明快です。
そして、明快なだけに思いは非常に深いものだったようです。
関東には生えていないバイオウカレンを、わざわざ故郷から取り寄せたこともあったのだとか。
バイカオウレンの真っ白な花が咲く光景は、牧野博士の心の原風景だったのでしょう。
牧野博士は最晩年、見舞いに来た方がバイオウカレンを持ってくるとたいそう喜んだそうです。
そのとき牧野博士の心は幼い子供に戻って、早春のバイオウカレンが一面に咲いている故郷の裏山を駆けまわっていたのではないでしょうか。

なお、バイカオウレンは牧野博士の故郷・高知だけでなく、東北南部から四国まで山林や雑木林に広く自生する日本固有種です。
四国には本来のバイオウカレンの他に、「シコクバイカオウレン」という変種も自生しています。
ちなみに、バイオウカレンの漢字表記「梅花黄連」ですが、花が梅の形(梅花)で、根が黄色い(黄連)ひげのようだからといわれています。

バイカオウレンには「ゴカヨウオウレン(五加葉黄蓮)」という別名もありますが、こちらは漢字のつづりのとおり、葉が5枚一組になっていることに由来します。
らんまん1週バイカオウレン|物語の関連と見どころ
らんまん1週の副題『バイカオウレン』は、万太郎の最愛の母・ヒサの1番好きな花として登場します。

母の思い出が詰まった特別な花として第1週以降にも出てくるなど、物語の原点となるような花です。
ドラマでは、死を目前にした母を元気づけたい幼い万太郎が、咲いているはずのない真冬に『バイカオウレン』を探し求めて山を歩き危険な目に遭うなど、涙なしでは見られない場面を演出しています。
ちなみに物語の舞台・高知県高岡郡佐川町(さかわちょう)は、バイカオウレンの群生地として有数の場所なのだとか。
そして万太郎のモデル・植物学者の牧野富太郎博士が幼い頃、最初に草花に興味を抱いた花が『バイカオウレン』だったと伝えられています。
牧野博士と同じように小さく可憐なバイカオウレンと出会い、どんどん植物の世界に引き込まれていく万太郎に注目の週です。
スポンサーリンク
【らんまん図鑑】2週キンセイラン
らんまん2週の花の名【キンセイラン】

らんまん2週キンセイラン|特徴
らんまん2週の『キンセイラン(金精蘭・金星蘭・金晴蘭・金清蘭)』(学名:Calanthe nipponica)は、ラン科エビネ属の多年草「エビネ(海老根)」の初夏咲きの原種のひとつです。
日本固有種で、北海道から九州まで、杉・赤松・ヒノキなどの森林や川沿いなど、湿度の高いところに生えます。
耐寒性はありますが、暑さに弱いのが特徴です。
高さは20~50cmで、葉は細長く先が尖っていて、毎年6~7月ごろに鮮やかな黄色の花を一株に3個から10個ほどつけます。
らんまん2週キンセイラン|花言葉

キンセイランの花言葉は「熱烈な愛情」「誇り高き心」「高貴なる女性」「美しい心」などです。
これらは、キンセイランの美しい凛とした立ち姿に由来しているといわれています。
薄暗くかすかな光しか射さない樹林の中に、黄色く輝くキンセイランの群生が突然現れると、その高貴で堂々とした黄色の群れに感銘を受けずにはいられなかったようですね。
らんまん2週キンセイラン|エピソード

キンセイラン(金星蘭)は、植物学者・牧野富太郎博士が37歳のときに学名を発表した、ラン科エビネ属の多年草です。
日本固有種で、海外には生息していません。
また、キンセイランは他の多くの品種と異なり、牧野博士が自ら収集したものでもありません。
東京帝国大学のある教授が採集した標本を皆で吟味している最中に、牧野博士が見つけ出して新種と判断し、命名したものなんだそうです。
このエピソードからも、牧野博士は37歳で、既に植物に関する卓越した見識と権威を持っていたことがわかりますよね。
キンセイランは、エビネ属の中では小さい部類に入りますが、その姿は「エビネの女王」と呼ばれるほど美しく、初夏に咲く花は鮮やかな黄色です。

和名の「金星蘭」は、花の色と美しい姿、そして葉や花茎が黄緑色を帯びることから「明けの明星」にたとえて牧野博士が命名しました。
ただしキンセイランの和名は「金精蘭」「金晴蘭」「金清蘭」とつづられることもあり、それらの出自は不明です。
キンセイランは、近年の環境変化やマニアの乱獲が原因で、もともと少なかった個体がさらに減少し、現在では絶滅危惧種に指定されてしまいました。
らんまん2週キンセイラン|物語の関連と見どころ
第2週の副題『キンセイラン』は、万太郎が『名教館・めいこうかん』で出会った恩師・池田蘭光(いけだらんこう)先生と学友・広瀬祐一郎の3人で1泊旅行に出かけた時に出会う花として登場します。

本の中だけでしか見たことのなかった希少な花・キンセイランを発見した万太郎は、心が震えるほどの感動を覚えます。
それと同時に、学びとは机の上だけでするものではなく、直接その植物に触れ、五感を通して感じることなのだと気づきました。
そんな万太郎に、蘭光は「心が震える先に金色の道がある。その道を歩いて行ったらえい!」という言葉を贈りました。
スポンサーリンク
【らんまん図鑑】3週ジョウロウホトトギス
らんまん3週の花の名【ジョウロウホトトギス】

らんまん3週ジョウロウホトトギス|特徴
らんまん3週の『ジョウロウホトトギス(上臈杜鵑草)』(学名:Tricyrtis macrantha)は、四国から九州に自生するユリ科ホトトギス属の耐寒性多年草です。
草丈は40~80cmで、先のとがった細長い卵型の葉の長さは8~14cmほど。
9月から10月ごろに、釣鐘型の花を1~2輪咲かせます。
つぼみは上向きですが、次第にうつむいて、花が開花するときは下向きになります。
花の色は外側が黄色ですが、内側にはホトトギス属の他の花と同様に、多くの赤紫色の斑点が見られます。
らんまん3週ジョウロウホトトギス|花言葉

*スルガジョウロウホトトギス
ジョウロウホトトギの花言葉は「あなたの声が聞きたくて」です。
黄色い花は、茎からたれ下がり、まるで鈴か小さな鐘のような形をしています。
その形を見ているうちに、聞こえるはずのない花の「声」が聞こえてくるような気分になるのかもしれません。
愛らしさと切なさのこもった花言葉です。
らんまん3週ジョウロウホトトギス|エピソード
ジョウロウホトトギスは、植物学者・牧野富太郎博士23歳(1885年)の時に、故郷の山で発見し命名した花です。
牧野博士が1888年に自費出版した『日本植物志図篇』第1巻・第1集の巻頭に掲載されるなど、この花に対する思いの深さがわかるような気がします。

ジョウロウホトトギスの仲間には土佐に生える「トサ(土佐)ジョウロウホトトギス」の他に、「キイ(紀伊)ジョウロウホトトギス」「サガミ(相模)ジョウロウホトトギス」「スルガ(駿河)ジョウロウホトトギス」という地域別の変種があります。
単に「ジョウロウホトトギス」と呼ぶ場合は「トサジョウロウホトトギス」のことを意味しています。

*サガミジョウロウホトトギス
どの種類のジョウロウホロロギスもすべて日本固有種で、すべて絶滅危惧種に指定されてしまいました。
これも、美しさゆえの乱獲が原因の一つとされています。残念です。
でも、森の中でこんなにも美しい出会いがあったなら、劇中の万太郎でなくともつい持って帰りたくなるのも分からなくはありませんね。
ジョウロウホトトギスを漢字で表現すると「上臈杜鵑草」ですが、杜鵑(ホトトギス)は鳥のホトトギスの意味で、花被片(カヒヘン)の内側の紫褐色の斑点がある様子をこの鳥の胸の斑点に見立てたものです。
そして上臈(ジョウロウ)は官職についた貴婦人のことを意味しています。
江戸時代の大奥では、高い役職についた女性のことを上臈と呼びました。
牧野博士は、この野草の中に限りない気品や凛々しさを感じたのではないでしょうか。
著書『新分類 牧野日本植物図鑑』では、ジョウロウホトトギスのことを「まるで夜空に浮かぶ星のような美しさを持つ花である」と表しています。
らんまん3週ジョウロウホトトギス|物語の関連と見どころ

*らんまんより©NHK
らんまん3週の副題『ジョウロウホトトギス』は、青年になった万太郎が高知の横倉山へ植物採集に出かけた際に、初めて出会う花です。
山中でジョウロウホトトギスに見惚れているうちに、万太郎は造り酒屋『峰屋』の年に一度の行事『蔵入りの日』に遅刻し、ひんしゅくを買う展開へと繋がります。
次期当主としての自覚に欠け、造り酒屋『峰屋』当主の祖母・タキや姉・綾を始めとする周囲に迷惑をかける一方、青年に成長してからも草花にとことん夢中である様子がジョウロウホトトギスと共に描かれます。
ちなみにジョウロウホトトギスは、タイトルバックのファーストカットにも選ばれている植物です。
あいみょんが歌う主題歌『愛の花』と合わせて、ツリガネ型のかわいらしい花の姿にも注目してくださいね。
スポンサーリンク
【らんまん図鑑】4週ササユリ
らんまん4週の花の名【ササユリ】

らんまん4週ササユリ|特徴
ササユリ(笹百合、学名:Lilium japonicum)は、中部地方から九州にかけて分布するユリ科ユリ属の多年草です。
日本固有種で高さは50~100cmくらい。
毎年6~7月ごろに大輪で淡いピンクの花を横向きに咲かせます。
まれに白い花が咲くこともあり、花の大きさは10~15㎝の漏斗状で強い香りがします。
ササユリという名称は、葉の形が笹の葉に似ていることに由来します。
笹と混じって生えていると、花が咲かないときは双方の見分けがつかないほどなんだそうですよ。
らんまん4週ササユリ|花言葉

ササユリの花言葉は「上品」「清浄」「希少」です。
このうち「上品」と「清浄」は、横向きに花を咲かせる様子が美しく上品で清々しいため付けられました。
「立てば芍薬、座れば牡丹、歩く姿は百合の花」という言葉を連想します。
これに対して「希少」は、種をまいてから十分に成長するのに何年もかかり、めったに花を見られないことに由来するそうです。
らんまん4週ササユリ|エピソード

ササユリ(笹百合)は、古事記には「山由理草・ヤマユリソウ」という名前で、万葉集には「サユリ花」という名前で登場するなど、古代から日本人に親しまれてきた花です。
古事記によると、神武天皇が後に皇后となる女性と出会い、恋をした川のほとり一面にササユリが咲いていたと描かれています。
このロマンチックな物語からもわかるように、1,200年以上前から日本の風土に馴染んで存在しているササユリですが、栽培するのが非情に難しいというデリケートな一面もあります。

環境の変化や病虫害にとても弱く、種から花が咲くまでに5年から8年(場合によってはそれ以上)もかかります。
鱗茎(球根)を採取して植えておけば翌年には花を見せてくれるものの、多年草にもかかわらずいつの間にか姿を消してしまい、毎年花を楽しむことはできません。
なお鱗茎は、漢方の世界で「百合(びゃくごう)」という名の生薬として使われる場合があります。

*ヤマユリの鱗茎
栽培の難しさや花の際立った美しさのため野生の株が盗掘される場合も多く、気候の変化なども相まって、近年では野生のササユリを見かける機会が少なくなりました。
そのため、残された自生地では保護活動を行う団体も増えています。
らんまん4週ササユリ|物語の関連と見どころ

第4週のテーマ植物『ササユリ』は、姉・綾が密かに思いを寄せていた蔵人・幸吉に妻がいると知り、傷心を胸に山道を引き返す時に登場する花です。
その場から逃げるように、山道を慌てて走った綾は派手に転んでしまいます。
傷心の中、体を起こそうとしたその時、一輪のササユリが凛と咲いていることに気づく綾。
そして、綾がポツンと咲くササユリを見つめ、思わず頬をゆるめるシーンは本当に美しくも悲しい名場面でした。
ササユリの品格ある姿と共に、綾の複雑な心中を繊細に演じる佐久間由衣さんに絶賛の声が寄せられました。
スポンサーリンク
【らんまん図鑑】5週キツネノカミソリ
らんまん5週の花の名【キツネノカミソリ】

らんまん5週キツネノカミソリ|特徴
キツネノカミソリ(狐の剃刀、学名Lycoris sanguinea)は、本州・四国・九州の雑木林などに生息する、ユリ科ヒガンバナ属の多年草です。
毎年8~9月ごろ、何もない地面から突然50cmほどの茎を伸ばし、オレンジ色の花を咲かせ、やがて完全に消えてしまいます。
春になると同じ場所から細長い葉がたくさん伸びますが、夏になると枯れて、再び花の季節を迎えます。
有毒で、鱗茎(球根)を作り増えていきます。
らんまん5週キツネノカミソリ|花言葉

キツネノカミソリの花言葉は「妖艶(ようえん)」です。
魅力的ですが、同時にどこか危険な雰囲気を漂わせる言葉です。
たしかに、うっそうとした森の中でこの花を見つけたら、ちょっと息をのむこと間違いなしですよね。
花の名前に付いた「キツネ(狐)」から、絶世の美女に化けて男性を惑わす狐の妖怪をイメージしているのかもしれません。
また、キツネノカミソリが毒を含む植物であることも、関係があるかもしれませんね。
らんまん5週キツネノカミソリ|エピソード

キツネノカミソリ(狐の剃刀)という変わった名前がこの植物に付いた理由は葉の形にあります。
葉の長さ30~40cm・幅1cm弱と細長く鋭いため、まるでカミソリのように見えたからです。
植物学者・牧野富太郎は「狐の剃刀とはその狭長な葉の形に基づいた名」と述べ、同時に「狐も時には鬚でも剃っておめかしをするとみえる。」とコメントしています。
一方このカミソリのような葉がなぜ「狐」のものとされているか、という点については、次のように諸説あって興味深いです。

・花の色が少しくすんだ赤茶色で狐の毛皮の色に見える。
・葉が無くなった後で突然茎が伸びて花が咲き、咲き終わると地上から消えてしまう様子が「狐に包まれたよう」だから。
・林の中などで突然花が咲く姿が、狐火のようだから。
・狐の住んでいるような山の中に自生する花だから。等々。
キツネノカミソリは、仲間のヒガンバナと同じように毒を含んだ植物です。
特に鱗茎(球根)の部分に毒が多く含まれています。

ただしその鱗茎には栄養分も含まれており、昔の人はわざわざ毒抜きをして食べることもあったようです。
中毒症状は睡眠作用・痙攣・吐き気・下痢などを引き起こすそうで、不用意に口にすると危険ですね。
らんまん5週キツネノカミソリ|物語の関連と見どころ

第5週のテーマ植物『キツネノカミソリ』は、自由民権運動の結社『声明社』リーダー・早川逸馬(はやかわいつま)の仲間と見なされて警察に収監された万太郎が、祖母・タキの人脈によって解放され佐川村へ帰る途中に登場します。
万太郎が道端で見つけるキツネノカミソリは、鮮やかなオレンジ色の花を咲かせる植物です。
ちなみに逸馬は万太郎が解放されるように嘘の証言をし、そのまま収監されてしまいます。
万太郎は自分だけが解放され、後ろ髪を引かれる思いで山道を歩く中、キツネノカミソリと出会います。

逸馬のトレードマークの羽織と同じ色をしたこの花を見て、万太郎や同行している姉・綾、お目付け役・竹雄が逸馬に思いを馳せるシーンは必見です!
【らんまん図鑑】6週ドクダミ
らんまん6週の花の名【ドクダミ】

らんまん6週ドクダミ|特徴
ドクダミ(学名:Houttuynia cordata)は日本国内のいたる場所で見かけるドクダミ科ドクダミ属の多年草です。
さらに、日本だけでなく、中国や東南アジアにも広く分布しています。
草丈は15~35cmほどで、暗い緑色のハート型の葉が特徴です。
5~7月に白い十字型の小さな花を咲かせます。
生命力が旺盛で、地下茎で増え全草に独特の臭いがあります。
「ドクダミ」という名前は「毒痛み」が転じたといわれ、万能民間薬としても用いられています。
らんまん6週ドクダミ|花言葉

ドクダミの花言葉は「野生」「白い追憶」「自己犠牲」です。
「野生」はいくら抜いても次々と生える、しぶとい生命力に由来すると言われています。
「自己犠牲」は、ドクダミが加工されることで色々と役立ってくれることを表しています。
さらに「白い追憶」は、ドクダミが咲いている広場や公園で遊んだ、あの白い花と独特の香りが忘れられないなど、まさに記憶のどこかに残るイメージからでしょうか。
らんまん6週ドクダミ|エピソード

ドクダミは、さまざまな有効成分を持つ有用で便利な薬草と思う人もいますし、その逆に、独特の臭いや旺盛な繁殖力から嫌な雑草と思う人もいます。
一重咲きの十字形が最もポピュラーなドクダミですが、八重咲きだったり葉に白や黄色や赤の斑がはいったりする、鑑賞用の品種も存在します。

薬草としてのドクダミは、ゲンノショウコ・センブリと共に「日本の三大薬草」と呼ばれるほど有用なのだとか。
ドクダミの茎や葉を乾燥させたものは、利尿作用・動脈硬化の予防・解熱や解毒など10の効能がある「十薬(じゅうやく)」としても知られています。
利用方法は、煎じてお茶として飲む方法や、生のドクダミの葉を揉んで火傷や傷口に当てて治療に使うこともあります。まさに万能薬ですね。

しかし、その一方でドクダミの生命力は非常に強く、地下茎を伸ばしてどんどん繁殖します。
ドクダミの駆除には除草剤を使ったり、熱湯をかけたり、表面を刈り取って重曹を撒くなどの方法がありますが、一番確実なのは根から完全に引き抜いてしまう方法です。
ただこの方法は大変に手間がかかります。

健康に良いからドクダミを栽培してみたいと考える人は、栽培場所などを慎重に考えるべきかもしれませんね。
らんまん6週ドクダミ|物語の関連と見どころ
第6週のテーマ植物『ドクダミ』は、上京した万太郎と竹雄が、盗まれた標本入りのトランクを探す中でたどり着く十徳長屋(じっとくながや)の敷地に生えている草花です。

十徳長屋は通称『クサ長屋』と呼ばれ、独特な匂いを持つドクダミの生える長屋だと周囲から揶揄されています。
しかし長屋の住人と出会い、下宿先が見つからなかった万太郎と竹雄は部屋を貸してもらう展開になります。
ドクダミは匂いのせいで嫌われがちですが、昔から解毒や利尿作用のある薬草として役立てられてきた植物でもあります。
共に暮らす十徳長屋の住人たちも、周囲から敬遠されていますが、付き合ってみると面白く優しい人たちだと分かってくる万太郎。
新生活の中でドクダミとも重なる十徳長屋の住人たちと万太郎が、関わりを深めていくシーンに注目です!
【らんまん図鑑】7週ボタン
らんまん7週の花の名【ボタン】

らんまん7週ボタン|特徴
ボタン(牡丹、学名:Paeonia suffruticosa)は、ボタン科ボタン属の落葉小低木です。
高さは1~1.5mほどで、毎年4~5月に大輪の花を咲かせます。
色は白・ピンク・赤・紫・黄、形は一重・八重・千重・万重・獅子咲きなど、品種はとても多いようです。
原産地は中国大陸の北西部で、日本には奈良時代に渡来しました。
その後、日本でも改良が進んでさまざまな品種が生まれました。
欧米でも改良が行われ、フランスボタンやアメリカボタンなどが誕生しています。
らんまん7週ボタン|花言葉

ボタンの花言葉は「王者の風格」「富貴」「恥じらい」などです。
「王者の風格」と「富貴」は、原産地の中国で大きく豪華な花姿を讃えて「百花の王」「花王」と呼んだことに由来しています。
これに対して「恥じらい」は、西洋由来の花言葉です。
中央にある花芯を隠すように花びらが重なって咲く様子が、恥ずかしそうに見えるというのがその理由です。
東洋と西洋の感性の違いが伺えて興味深い花言葉ですね。
らんまん7週ボタン|エピソード

ボタンの花と人類の関わりは古くからあったようです。
もともとは根の樹皮部分を薬用に栽培していたのですが、原産地の中国では、唐の時代には観賞用の花としても一大ブームが起こりました。
詩人・白居易(白楽天)はボタンの人気について「街中の人が狂ったようだ」と述べています。
中国ではこの時代以降、ボタンの花が詩歌に盛んに登場するようになりました。

たとえば李白や白居易といった唐時代の有名な詩人が、絶世の美女としてよく知られる楊貴妃のことをボタンの花にたとえた詩を読んでいます。
日本では奈良時代に薬用植物として中国から輸入され、平安時代から観賞用としての栽培が始まりました。
清少納言は『枕草子』でボタンについて触れていますが、これが日本文学にボタンが登場した最古の記録と言われています。

時代が下って江戸時代(元禄期)になると、観賞用のボタンの栽培が盛んになり、多くの園芸品種が誕生し今日に至ります。
らんまん7週ボタン|物語の関連と見どころ

第7週のテーマ植物『ボタン』は、万太郎が好きな花を質問した時に、『白梅堂』の娘・寿恵子がその名を口にする花です。
この時、寿恵子は読本『南総里見八犬伝』にハマっていて、メインキャラクターの『八犬士』たちが体のどこかにボタンのアザを持つストーリーを思い出し、万太郎に「ボタン」と答えます。
そして、偶然、植物学教室でボタンを見かけた万太郎は、得意の植物画を描き寿恵子にプレゼントするという展開になります。
万太郎が『ひと目惚れ』するほど愛らしい寿恵子の華やかな美しさに、ぴったりなテーマですよね。
この頃には、お互いのことを少しずつ意識しはじめている万太郎と寿恵子。
ボタンの植物画を眺めながら会話をする2人の初々しい様子も、第7週の見どころになりそうです!
【らんまん図鑑】8週シロツメクサ
らんまん8週の花の名【シロツメクサ】

らんまん8週シロツメクサ|特徴
シロツメクサ(白詰草、学名: Trifolium repens)は、マメ科シャジクソウ属の多年草です。
今日では、クローバーという英名の方が通りが良いかもしれません。
草丈は10~20cmで三つ葉が基本で、4~7月には白く丸い花(小さい花の集合体)をたくさん咲かせます。
シロツメクサは丈夫で繁殖力が強く、至る所で見かけます。
根には根粒菌が共生していて土に窒素(肥料の成分のひとつ)を固定するため、緑化に用いられることもあります。
らんまん8週シロツメクサ|花言葉

シロツメクサの花言葉は「幸運」「私を思って」「約束」「復讐」です。
「幸運」は四つ葉を見つけると幸せになるという話、「私を思って」は、シロツメクサの花冠を編んで恋人に贈り、受け取ってもらえたら幸せになれるという話に基づきます。
「約束」はキリスト教に基づく習慣が由来なんだそうです。
でも、「復讐」は、ちょっと怖い言葉ですね。
これは他の花言葉に込められた幸運が叶わなかったときに「復讐」へつながるという意味なんだそうですよ。
花言葉って結構複雑なものなんですね。
らんまん8週シロツメクサ|エピソード

「シロツメクサ」より英名の「クローバー(Clover)」と呼んだ方がわかりやすいかもしれません。
道端に生えているクローバーの群れの中から、四つ葉を見つけようと必死になって探した経験は、誰もが一度はあるのでは?
また、ふわふわとした白く丸い花の群れの中に座り込んで、冠や首飾りを夢中で作った人も多いと思います。
シロツメクサは、明治時代の始めに牧草として種が輸入され、日本に広まった帰化植物です。

しかし、シロツメクサが日本で知られるようになったのは、さらに昔の江戸時代のことでした。
1846年にオランダから将軍家にガラスの花瓶が献上されたとき、花瓶が割れないための詰め物として乾燥したシロツメクサが使われていたことが知られています。
和名の「シロツメクサ」の名はこのエピソードに由来していると言われています。
ガラスが割れないための「詰め物」として使われている「花が白い」草なので、「シロツメクサ(白詰草)」となったのだとか。
話は変わりますが、海の向こうのアイルランドでは、シロツメクサの三つ葉は「シャムロックShamrock」という名で、国のシンボル的存在となっています。

この地にキリスト教を広めた聖パトリックが、「三位一体(さんみいったい)」という教義を説明するためにシャムロックを用いたそうです。
アイルランドの国の色はこのシャムロックにちなみ緑色で、聖パトリックの記念日には国中が緑一色に染まるんだそうですよ。
らんまん8週シロツメクサ|物語の関連と見どころ
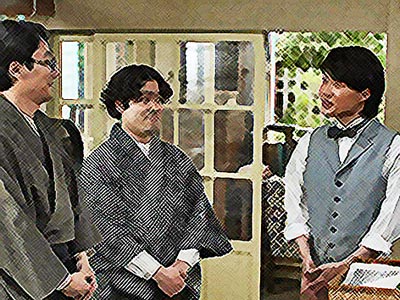
第8週のテーマ植物『シロツメクサ』は、万太郎が『雑司が谷』(ぞうしがや)の牧場で植物学教室の2年生・藤丸の飼っているウサギのためにお土産として詰んでくる草花です。
この時、万太郎は植物学教室の面々から他所者扱いされ孤立していますが、このシロツメクサのおかげで学生らと仲良くなれるきっかけを掴みます。
ちなみにシロツメクサはヨーロッパ原産ですが、現在は日本中のどこでも見られる帰化植物です。
また、通常3つ葉ですが4つ葉は『幸運を呼ぶシンボル』とも言われています。
そのため、劇中で孤独から解放された万太郎が、幸運を運んでくれた4つ葉のシロツメクサに感謝するシーンは必見です!
【らんまん図鑑】9週ヒルムシロ
らんまん9週の花の名【ヒルムシロ】

らんまん9週ヒルムシロ|特徴
ヒルムシロ(蛭蓆、学名:Potamogeton distinctus)は、ヒルムシロ科ヒルムシロ属の多年生の水生植物で、日本全国の池や水田、小川などに生育します。
原産は日本・中国・朝鮮半島です。
水中には線状の水中葉があり、水面には水をはじく楕円形の葉が浮いています。
6~10月には葉の付け根から柄が出て、長さ3~6cmで棒状に集まった黄緑色の小さな花を咲かせ、秋になると茎の先が膨らんで越冬芽を作ります。
らんまん9週ヒルムシロ|花言葉

ヒルムシロの花言葉は「清らかな愛」「清純な心」「思いやり」です。
この花言葉は、清楚で優雅なヒルムシロの姿に由来していると言われています。
ヒルムシロの花は、決して派手ではありませんが、それが「清楚で優雅」と形容される由来となったようです。
蛭(ヒル)がいっぱい住んでいる田んぼや池に繁茂している水草としては、意外なほど上品な花言葉ですね。
らんまん9週ヒルムシロ|エピソード

ヒルムシロ(蛭筵)という変わった名前は、水面に浮かぶ葉を蛭(ヒル)が乗って休憩をするための筵(ムシロ)に見立てて名付けられたものです。
ただし、ヒルムシロと蛭の間には、特別な共生関係はありません。
ヒルムシロが水辺に小判型の葉を浮かべている様子はとても優雅ですが、繁殖力が旺盛なので、水面全体を葉で覆いつくすほど増えてしまうことがあります。

*ヒルムシロの群生
田んぼがそのような状態になると、水温を下げてしまうと同時に稲の養分まで吸収してしまいます。
そのため農家はヒルムシロを、いくら除去してもしつこく生える雑草として嫌っていました。
しかし、現在では有効な除草剤が開発されたので、田んぼを覆いつくすヒルムシロの姿も見かけなくなりました。

*キボウホウヒルムシロ
実はこのヒルムシロ、15世紀・中国の明時代に飢饉(ききん)の際に食用できる植物を解説した書『救荒本草(きゅうこうほんぞう)』にも掲載され、よく煮ると食べられると記されていました。
飢饉の時には、その繁殖力の強さから食用にもされていたんですね。
らんまん9週ヒルムシロ|物語の関連と見どころ

第9週のテーマ植物『ヒルムシロ』は、万太郎が沼地から採集した水草で、十徳長屋に持ち帰ってくるシーンで登場します。
この後、『白梅堂』の娘・寿恵子のことが頭から離れず、恋の病にかかり悩んでしまう万太郎。
そこで十徳長屋の住人のえい・りん・ゆうの女性陣が、水桶に浮かべたヒルムシロを囲んで、自らの経験談を交えながら万太郎を励ますシーンが待っています。
小さな水草を愛でながら酸いも甘いも噛み分けた女性3人が、恋愛初心者の万太郎にアドバイスするシーンは、ぜひチェックしたい見どころポイントです~♬
【らんまん図鑑】10週ノアザミ
らんまん10週の花の名【ノアザミ】

らんまん10週ノアザミ|特徴
ノアザミ(野薊、学名:Cirsium japonicum)は、キク科アザミ属の多年草です。
本州・九州・四国の日当たりの良い山野に生えていて、高さは50~100cmくらいです。
日本には100種類ほどのアザミの仲間が生息していますが、一般的にアザミといえばこのノアザミをさします。
葉の縁はギザギザで鋭いトゲがあり、5~8月に赤紫色で直径が4~5㎝もある花を咲かせます。
まれに淡紅色や白い花が咲くこともあるんだそうですよ。
らんまん10週ノアザミ|花言葉

ノアザミの花言葉は「触れないで」「素直になれない恋」「権利」「私をもっと知って下さい」等、たくさんあります。
そして由来はすべて鋭いトゲにあるようです。
「触れないで」は、文字通り「トゲがあるから触らないで欲しい」という意味です。
「素直になれない恋」はトゲのせいで近寄り難いことを「素直になれない」と表現し、「権利」と「私をもっと知って下さい」ではトゲに強い自己主張を託したと言われています。
らんまん10週ノアザミ|エピソード

ノアザミを含むアザミの仲間の特徴は、美しい花と鋭いトゲです。
そして鋭いトゲは、ときとして思いがけないエピソードを引き起こします。
大昔(10世紀ごろ)スコットランドにノルウェーの軍隊(ヴァイキング)が攻め込んできた時もそうでした。
裸足でこっそりと侵入してきたヴァイキングの兵士のひとりがアザミを踏んでしまい、思わず声を上げスコットランド兵たちに気づかれてしまったといいます。
その結果、スコットランド軍は見事に大反撃を行い、国を守る事に成功したという伝説が伝わっています。

*オニアザミ
この話の真偽は不明ですが、スコットランドが「国を救った花」として、アザミを国花に定めているのは紛れもない事実です。
スコットランドの最高の勲章であるシッスル勲章(Order of the Thistle)も、アザミがモチーフになっています。
トゲの痛みで人をひどい目に遭わせるアザミですが、意外なことに食用にすることも可能な植物なんですよ。
春の若いノアザミの葉はトゲもまだ柔らかく、天ぷら・和え物・汁の実・煮物などにして食べられるそうです。

ノアザミは花や根も食用にできて、花は酢の物や花酒に、根は「山ごぼう」という名できんぴらやみそ漬けなどにして食べられます。
らんまん10週ノアザミ|物語の関連と見どころ

第10週のテーマ植物『ノアザミ』は、万太郎が植物雑誌を作るため印刷と大学の研究の両方に取り組む中、通学路の途中で見つけいつものように話しかけるシーンに登場します。
ちょうどこの頃、万太郎は、植物雑誌の完成という目標を達成できたら寿恵子に思いを伝えようと、会いに行くのを我慢し頑張っている最中です。
一方、寿恵子は会いに来ない万太郎にしびれを切らし、実業家・高藤から申し込まれた結婚話に心が揺らいでしまいます。
花言葉通り「素直になれない恋」?
そして、道端のノアザミが、離れかけた寿恵子の心を引き戻すシーンは、視聴者も大拍手のエピソードとなりそうです。
【らんまん図鑑】11週ユウガオ
らんまん11週の花の名【ユウガオ】

らんまん11週ユウガオ|特徴
ユウガオ(夕顔、学名:Lagenaria siceraria)は、ウリ科ユウガオ属のつる性一年草です。
原産地は北アフリカと熱帯アジアで、日本には中国を通じ平安時代に渡来しました。
暑い7~8月の夕方に白い花を咲かせますが、その花は翌朝にはしぼんでしまいます。
朝顔・昼顔・夜顔などの仲間かと思われますが、これらは皆ヒルガオ科でユウガオの仲間ではありません。

*画像は朝顔。これら朝顔・昼顔・夜顔とユウガオは科が異なります。
意外に思えるかもしれませんが、ユウガオはヒョウタンの仲間で、秋には大きな実をつけます。
らんまん11週ユウガオ|花言葉

ユウガオの花言葉は「はかない恋」「夜の思い出」「魅惑の人」「罪」です。
「はかない恋」は夏の夕方に咲いて、翌朝にはしぼんでしまうユウガオ花のはかなさに由来します。
「夜の思い出」は、暗くなってから花が咲き始めることから付いたと言われています。
一方「魅惑の人」と「罪」は、源氏物語に登場する夕顔の君という女性に関係しています。
光源氏に愛されたにもかかわらず、最後は物の怪に襲われて亡くなってしまう薄幸の女性でした。
らんまん11週ユウガオ|エピソード

ウリ科の植物らしく、ユウガオは秋になると大きな実をつけます。
細長い実をつけるナガユウガオと、丸い実をつけるマルユウガオの2種類に分かれます。
仲間のヒョウタンと違い、ユウガオは食用にもなります。
そして、淡泊な味わいで、どんな料理にも味がなじみやすいという特徴もあります。
おいしい食べ方としては、油揚げなどと一緒に煮物にしたり、薄く切って味噌汁の具や酢の物にしたりするなどがあげられます。

種やワタを取り除いてから薄切りにして、豚肉などと炒めてもおいしいそうですよ。
特にマルユウガオは、実を薄く剥いて細い紐状にして乾燥させると、巻きずしの具などでおなじみのカンピョウになります。
栃木県南部は日本のカンピョウの代表的な生産地で、日本のカンピョウの8割以上は栃木県産です。
しかし、ユウガオの仲間の中には、ヒョウタンをはじめ、実が苦くて食べられない種類もあります。

*ヒョウタン
この苦い成分は毒なので、うっかり食べてしまうと危険です。
地方では、苦いユウガオの実を食べて、中毒を起こすことがときどきあるようです。
らんまん11週ユウガオ|物語の関連と見どころ

第11週のテーマ植物『ユウガオ』は、万太郎が東京大学の敷地内で折り合いの悪い助教授・徳永と話すシーンに登場します。
地面にはいつくばってヒルガオと同時に咲くユウガオを観察している万太郎に、珍しく徳永はアサガオ・ヒルガオ・ユウガオの中で仲間外れはどれかと質問するのです。
めずらしく、いつも対立しがちな徳永と他愛のない会話をわずかながらも楽しめた万太郎。
徳永が去った後、ユウガオに感謝の気持ちを伝える万太郎らしいシーンが見どころです。
ちなみにユウガオは第11週の終盤で、実業家・高藤のプロポーズを断った寿恵子が十徳長屋にいる万太郎の元へ駆けつけるシーンにも登場します。
このシーンに、白い花を咲かせるユウガオのようなドレスで登場する、美しい寿恵子の姿にも注目です!
【らんまん図鑑】12週マルバマンネングサ
らんまん12週の花の名【マルバマンネングサ】

らんまん12週マルバマンネングサ|特徴
マルバマンネングサ(丸葉万年草、学名:Sedum makinoi)ベンケイソウ科マンネングサ属の常緑性多年草です。
草丈は5~20㎝ほどで、日本では本州・四国・九州の岩場や石垣などに自生しています。
毎年6~7月になると、茎を伸ばして黄色い星型の花を数個咲かせます。
花は直径1㎝弱しかありませんが、一度にたくさん咲くので、最盛期には株が黄色に染まります。
らんまん12週マルバマンネングサ|花言葉

マンネングサの花言葉は「枯れることのない愛」「私を想ってください」「静寂」「星の輝き」などです。
「枯れることのない愛」は、水が少なくても枯れないことに由来するようです。
「私を想ってください」と「静寂」は、一見地味なマンネングサが「想って頂戴」と、静かに語りかけているように感じさせるからだと言われています。
「星の輝き」は、マルバマンネングサがそうであるように、5枚ある花弁のおかげで花がきらめく星のように見えることに由来するようです。
らんまん12週マルバマンネングサ|エピソード

マルバマンネングサの学名「Sedum makinoi」の「makinoi(マキノイ)」は、この植物の学名が牧野富太郎の名にちなんで付けられたことを示しています。
ただし、この学名を命名したのは富太郎自身ではありません。
ロシアの植物学者でサンクトペテルブルク帝立植物園標本館の学芸員・展示企画者であったカール・ヨハン・マキシモヴィッチです。

来日して実際に植物の調査を行った経験もあるマキシモヴィッチは、草創期の日本の植物学の分野において、重要人物と位置付けられていました。
そのため当時の日本の植物学者たちは、未知種や新種と思われる草花を採集すると、こぞってマキシモヴィッチの元へ標本を送り鑑定を依頼していたのでした。
そして、富太郎も、以前から標本を送って指導を仰いでいた研究者のひとりでした。
富太郎は、ロシアへ送った標本の中に新種と鑑定された植物が含まれているだけでなく、マキシモヴィッチがその学名に富太郎の名前を付けたことを知って当然のことながら大喜びしました。
当時、富太郎は26歳でした。

私生活において、愛する女性・小澤壽衛と結婚した頃でもあり、若い富太郎にとっては人生で最良の時期のひとつであったと思われます。
らんまん12週マルバマンネングサ|物語の関連と見どころ

第12週のテーマ植物『マルバマンネングサ』は、万太郎と寿恵子の縁談がまとまり、結婚の挨拶をしに佐川へ帰郷する道すがらに登場します。
この植物を知らない寿恵子のために、万太郎が冬でも枯れない植物で6月に小さくて黄色い花を咲かせるのだと教えてあげるシーンは、実にほほえましい場面になりそうです。
また、万太郎は、ロシアの植物学者・マキシモヴィッチ博士へ『土佐植物目録』を送り、検定を依頼していました。
その結果が実家『峰屋』に届き、『マルバマンネングサ』が新種として認められた事を知ります。
そして、驚くべきことに、槙野の名が刻まれた学名になることも知ります。
『マルバマンネングサ』は、万太郎が植物学者として認められる、そのきっかけとなる植物として登場します。
【らんまん図鑑】13週ヤマザクラ
らんまん13週の花の名【ヤマザクラ】

らんまん13週ヤマザクラ|特徴
ヤマザクラ(山桜、学名: Cerasus jamasakura)はバラ科サクラ属の落葉高木です。
本州や四国・九州に主に自生し、宮城県や新潟県が北限とされます。
日本に10~11種自生しているサクラ属の野生種のひとつで、高さは15 ~ 25mにもなります。
園芸種のソメイヨシノと異なり、花と葉が同時に開く特徴があります。
さらに、ヤマザクラの寿命は200~300年といわれていますが、中には樹齢500年を超える古木もあります。
寿命60年説があるソメイヨシノに比べてはるかに長命ですね。
らんまん13週ヤマザクラ|花言葉

ヤマザクラの花言葉は、「あなたに微笑む」「淡白」「純潔」「高尚」「美麗」などです。
このうち「あなたに微笑む」は、春先の山河の何も咲かない時期に、可憐なヤマザクラの咲く様を見ると、思わず微笑んでいるかのように見えることを表したといわれています。
「淡泊」は花の寿命が短く、あっさりと散ってしまう様子を示したもので、「純潔」は見た目の清らかさ、「高尚」は俗っぽくない様子、「美麗」ははっとするほどの美しさを表していると言われています。
まさに桜のイメージそのものですね。
らんまん13週ヤマザクラ|エピソード

ソメイヨシノが幕末に生まれて広まるまで、日本で「桜」といえば、『ヤマザクラ』のことでした。
平安時代以降、江戸時代までの間に歌で詠まれたり、絵に描かれたりした「桜」のほとんどはヤマザクラでした。
ヤマザクラの花は、白や淡いピンクです。
ソメイヨシノとよく似ていますが、野生種なので個体差も大きく、ソメイヨシノのように一斉に花が開いて一斉に散ってしまうこともありません。
ヤマザクラの木は硬く湿気に強いため、上質な材木として家具の材料などに使われています。

サクラの木といえば、有名なジョージ・ワシントンのエピソードが思い浮かびます。
アメリカ合衆国初代大統領のジョージ・ワシントンが少年時代に大切なサクラの木を切ってしまい、そのことを父親に打ち明けたところ、怒られるどころか返って正直さをほめられたという話です。
西洋のサクラの花言葉には、この話題をもとにした「優れた教育」が含まれているそうです。
もちろん伝説の真偽は定かではないし、切られた木も日本のヤマザクラとは違うのかもしれません。

*エゾヤマザクラ
でも、日本では春の卒業・入学シーズンの象徴にもなっているサクラが、西洋でも「優れた教育」の花言葉で知られている事実は、興味深いことと感じます。
らんまん13週ヤマザクラ|物語の関連と見どころ

第13週のテーマ植物『ヤマザクラ』は、万太郎の祖母・タキが懇意にしている呉服店の庭に昔からある桜として登場します。
ある日、寿恵子の花嫁衣装をあつらえるため呉服店の主人を呼んだタキ。
2人が世間話をする中で、呉服店の庭の『ヤマザクラ』が病気になり、切り倒さなければならない事を知ります。
そこでタキは草花に詳しい万太郎に、桜をなんとか助けられないかと相談します。
しかし、手を尽くしますが根治は出来ないとわかる万太郎。
最後の手段として若い枝を挿し木(さしき)にして、未来に望みを繋ぐことにします。
第13週では、峰屋をめぐる世代交代も同時に描かれます。
病に犯されたヤマザクラと、峰屋を最後まで気丈に支えきったタキが重なる、切なくも美しいシーンは必見です!
【らんまん図鑑】14週ホウライシダ
らんまん14週の花の名【ホウライシダ】

らんまん14週ホウライシダ|特徴
ホウライシダ(蓬莱羊歯、学名:学名Adiantum capillus-veneris)は、ホウライシダ科ホウライシダ属のシダの仲間です。
日本でも江戸時代から園芸用に栽培されていて、現在では「アジアンタム」としてよく知られています。
アジアンタムは、世界の温帯から熱帯に250種類から300種類が分布していて、光沢のある黒っぽい茎とハート型やイチョウ型にたとえられる小さな葉が共通しています。
らんまん14週ホウライシダ|花言葉
ホウライシダ(アジアンタム)の花言葉は「繊細」「天真爛漫」「上機嫌」「無邪気」です。
「繊細」は、細かくやわらかい葉がたくさん重なり合ってレースのように見えることに由来します。
「天真爛漫」は英語名がMaiden hair fern(乙女の髪のシダ)であることによるといわれます。
「上機嫌」「無邪気」からも同じようなイメージを受けます。
らんまん14週ホウライシダ|エピソード
ホウライシダはアジアンタムという名前で、観葉植物として広く栽培されています。
シダ植物なので胞子で増えるため、花が咲いたり実がなったりすることはありませんが、それでも上記のように「花言葉」がある、という不思議な面もあります。
なお、ホウライシダ(アジアンタム)には「アジア」という名前が含まれていますが、アジア原産の植物ではなく、世界中の熱帯から温帯にかけて広く分布しています。
アジアンタムという名前は、ギリシャ語に由来する合成語で、「a(無)」と「dianotos(濡れる)」を組み合わせた「adiantos(濡れない)」という意味なのだとか。
ホウライシダ(アジアンタム)の葉には撥水性があり、葉が水分をはじくことによります。
ちなみに和名のホウライシダ(蓬莱羊歯)の由来は、桃源郷(俗界を離れた仙人の理想郷)を意味する「蓬莱」です。
日本では関東以西に自生していますが、その愛らしい姿から既に江戸時代に観葉植物として栽培されていたため、いろいろな場所に国内帰化した株が広がっています。
観葉植物としての価値だけでなく、風水の面でも有用で、パワーの落ちた陰の気を吸い取る効果があるといわれています。
ホウライシダは日陰の湿った場所でも育つので、陰の気のたまりやすいトイレに置いてみてください。
また、リラックスして安眠したい寝室にも、陰の気と相性の良いホウライシダは効果的だそうですよ。
小さな葉が下向きにたくさん生えているホウライシダは陰の気を吸収するだけでなく、金運を上げる効果もあるといわれています。
ホウライシダの鉢を西の方角に置くとよいのだとか。
特にキッチンは水の気と火の気が入り乱れているのですが、ホウライシダの小さな鉢を置くことで空間が中和され、気の流れがスムーズになるのだそうですよ。
ぜひ試してみてください!
らんまん14週ホウライシダ|物語の関連と見どころ

第14週のサブタイトルとなる『ホウライシダ』は、東大の田邊教授の好きな植物として登場します。
結婚を祝うために田邊は、自宅に万太郎と寿恵子を招待。
田邊の自宅の庭でホウライシダを見つけた万太郎はテンションが上がります。
寿恵子と田邊の妻・聡子が親しくなる一方で、田邊は学歴もなく留学経験もない万太郎が植物研究者として認知されることはないと言い放ち、自分専属のプラントハンターになれと強く迫ります。
結果的に万太郎はその提案を断り、田邊を憤慨させることに。
そんな田邊は、「シダは花も咲かせず種も作らない」と前置きした後に、花が咲く植物よりも前に地球上に存在していたと学術的な説明をします。
そして好きな理由として「太古の昔、胞子だけで増えるシダ植物は陸の植物の覇者。地上の植物の始祖にして永遠」と聡子に打ち明けます。
さらに聡子の着物の帯は『シダ紋』で、田邊のお気に入りなのだとか。
普段は明かさない田邊の心の内がホウライシダを通して描かれます。
【らんまん図鑑】15週ヤマトグサ
らんまん15週の花の名【ヤマトグサ】

らんまん15週ヤマトグサ|特徴
ヤマトグサ(大和草、学名:Theligonum japonicum Okubo et Makin)はアカネ科ヤマトグサ属の多年草です。
日本固有種で、本州の関東以西・四国・九州に分布し、山地の森に自生しています。
どことなくハコベに似た目立たない多年草で雌雄同株です。
雄花は雄しべがヒゲのように垂れ下がった形、雌花は小さくて目立ちません。
風の媒介で受粉をする風媒花で、4月から5月に花が咲きます。
らんまん15週ヤマトグサ|花言葉
ヤマトグサの花言葉は、残念ながらはっきりしていません。
「ヤマトグサの花言葉はありません」と断定している場合もあるほどです。
しかしその一方でヤマトグサの花言葉として「思いやり」「愛」「日常」の3種類を紹介しているケースもあります。
目立たない雌花ではなく、ヒゲのように垂れる雄花についての花言葉です。
どの言葉も、地味だけどやさしさを感じる、日本の山野草らしい花言葉です。
らんまん15週ヤマトグサ|エピソード
ヤマトグサ(大和草)という名前には「日本草」の意味が込められています。
らんまんの主人公・槙野万太郎のモデルとなった植物学者・牧野富太郎博士によって1884年(明治17年)に高知県で発見されました。
雌雄同株で雄花がヒゲのように垂れている姿のヤマトグサは、世界でも近縁種が4種類しかない珍しい存在。
日本国内に同じ種類の植物は存在しません。
そのため花が咲く4月から5月ごろにこの花を見た場合、ヤマトグサと特定するのは比較的簡単です。
しかし葉や茎だけの状態の時期にこの草を見かけた場合、ハシカグサという別の草と非常に似ているため、両者の区別は困難です。
牧野博士も最初はこの草をハシカグサと思っていたそうです。
しかし後により良い状態の標本を同じ場所から採集することができたため新種の植物とわかり、1887年(明治20年)に、同じ植物学者の大久保三郎(らんまんキャスト大窪のモデル)との連名で「植物学雑誌」に論文を発表しました。
ヤマトグサは日本固有種であり、日本人が発見したもので日本の学術雑誌に論文が掲載された初めてのケースです。
世界的に見ても、日本人によって学名(Cynocrambe japonicum Makino のちに Theligonum japonicum Okubo et Makin)が決定されたのは、伊藤篤太郎がトガクシショウマの学名をイギリスの雑誌に発表したのに次いで2例目です。
牧野博士が27歳の1889年(明治22年)のことでした。
らんまん15週ヤマトグサ|物語の関連と見どころ
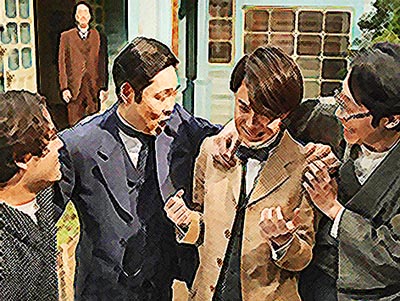
第15週の『ヤマトグサ』は、万太郎に転機をもたらす植物として登場します。
新種を名付け親になりたい万太郎は、誰もが認めるような植物学者を目指しています。
そんな中、高知から持ち帰った数多くの植物を、東大・植物学教室の講師・大窪昭三郎と共同研究することに。
田邊教授は研究をやめさせようとしますが、徳永助教授が説得することで共同研究は継続していきます。
やがて万太郎と大窪は新種として発見した植物を『ヤマトグサ』と命名し、植物学会誌で発表!
この発表は日本で植物学が始まって以来の快挙となり脚光を浴びることになります。
ヤマトグサの発表と自費出版の『植物図鑑』の発行によって万太郎は植物学者としての地位を固めていくことになります。
【らんまん図鑑】16週コオロギラン
らんまん16週の花の名【コオロギラン】

らんまん16週コオロギラン|特徴
コオロギラン(蟋蟀蘭、学名:Stigmatodactylus sikokianus)はラン科コウロギラン属の珍しいランです。
一属一種で、これ以外にコウロギラン属に属するものはありません。
国内では紀伊半島・四国(高知・徳島)・九州(宮崎・鹿児島)・伊豆諸島、海外では中国東南部や台湾で、自生地はスギ林や常緑広葉樹林の中で、落ち葉が堆積している場所です。
植物自体のサイズは3cmほど、花に至っては3mmほどの大きさしかありません。
らんまん16週コオロギラン|花言葉
コオロギランの花言葉を調べたものの見つかっていません。まだ花言葉がない可能性があります。
そもそも花言葉の歴史はギリシア・ローマ神話の時代にまでさかのぼるので、当時から人々に知られていた植物には花言葉がありますが、発見されて間もない植物や多くの山野草の場合、花言葉が無いこともしばしばです。
ひょっとしたらコオロギランにも、今後花言葉が付けられるかもしれませんね。
らんまん16週コオロギラン|エピソード
コオロギランは、らんまんのモデルで植物学者・牧野富太郎博士が新種として発表した植物のひとつです。
1989年(明治22年)数人で高知県の横倉山の安徳天皇御陵墓伝説地に近い林の中を散策中、牧野の友人のひとり吉永虎馬が、足元に見慣れない植物を発見しました。
さすがの牧野博士もその正体を特定できなかったため、ロシアの高名な植物学者のカール・ヨハン・マキシモヴィッチ博士に分類を依頼。
マキシモヴィッチ博士はそれを新種のランだと判断して「Stigmatodactylus sikokianus」という学名を付けました。
ちなみに「sikokianus」とは横倉山のある四国の意味だそうです。
しかしながら、マキシモヴィッチはその結果を公表する前にインフルエンザが原因で亡くなってしまいました。
そのため牧野博士は、花の形がコオロギに似ていることから、この新種のランに「コオロギラン」という和名を付けて、マキシモヴィッチからの返事の手紙と共に「植物学雑誌」などに発表しました。
マキシモヴィッチ博士はこの手紙の中で、牧野博士の描いた解剖図がとても正確で、マキシモヴィッチ自身が解剖したつぼみの様子と寸分たがわなかったと称賛しています。
牧野博士にとって尊敬するマキシモヴィッチ博士からのこの返事はとても嬉しかったことでしょうね。
らんまん16週コオロギラン|物語の関連と見どころ
第16週の『コオロギラン』は、万太郎が故郷の横倉山に植物採集に出掛けて発見する植物として登場すると思われます。
※詳しい内容が分かり次第、追記させていただきます。
【らんまん図鑑】17週ムジナモ
らんまん17週の花の名【ムジナモ】

らんまん17週ムジナモ|特徴
ムジナモ(狢藻、学名:Aldrovanda vesiculosa)はモウセンゴケ科ムジナモ属の多年生植物です。
水中を浮遊しながら成長する珍しい水生の食虫植物で、根がありません。
南北アメリカと南極大陸を除く世界中に分布していますが、生息地は全部で約50カ所といわれる希少植物。
しかも自生地の環境は年々悪化しているため、日本でも世界でも絶滅危惧種に指定されています。
らんまん17週ムジナモ|花言葉
ムジナモの花言葉は「待ち続ける恋」です。
ムジナモ自体も大変珍しい植物ですが、ムジナモの花はさらに珍しく、真夏の日中に年1回だけ開花して、1~2時間で閉じてしまいます。
また、つぼみを付けても花が咲くとは限らないた、ムジナモの花は「幻の花」と呼ばれています。
花は大きさ数ミリで白く可憐なものなので、見たい人にとって、永遠と思えるほど「待ち続ける恋」のような存在でしょう。
らんまん17週ムジナモ|エピソード
ムジナモは17世紀にインドで発見され、既に植物学者の間では、奇妙で希少な食虫植物として知られていました。
世界でもごくわずかの地域だけに生育していると考えられていました。
しかし日本でも自生していること、そしてそれまで花が咲かないと思われていたこの植物が、ごく稀ではあっても花をつけることを発見し、世界に発表したのが、らんまんのモデル植物学者・牧野富太郎です。
1890年(明治23年)5月、牧野博士は柳の実の標本を採集するために江戸川の土手に出かけました。
そこにあった用水池の周囲に柳の木が茂っていたため、枝を折ろうと木にもたれながら水面をのぞくと、何やら奇妙な植物が浮いていたのだとか。
早速すくい取って、東京帝国大学の植物学教室に持ち込みました。
誰もが驚いたその植物の正体を、教授の矢田部良吉(らんまんキャスト田邊のモデル)がAldrovanda vesiculosaであると突き当てたそうです。
牧野博士は和名を付けてその年の11月の「植物学雑誌」に発表。
和名のムジナモ(貉藻)はムジナ(アナグマ)の尻尾に似た食虫植物であることに、由来しているそうです。
牧野博士が描いた写生図には、それまで存在が知られていなかった『ムジナモの花』が描かれていたため注目を集め、ドイツで発刊された世界的な植物分類書に転載されます。
この結果、植物学者・牧野富太郎の名前も世界に知られることになりました。
らんまん17週ムジナモ|物語の関連と見どころ
第17週の副題となる『ムジナモ』は、万太郎が世界的に認知されるキッカケとなる植物です。
十徳長屋の近くの池のほとりで、見知らぬ水草を発見した万太郎。
早速、東大・植物学教室にその植物を持ち込むと、田邊教授が興奮します。
実はムジナモは世界各地で見つかっているものの、日本で発見されたのは初めてなのだとか。
とんどもない発見だと言う田邊は、万太郎に世界に向けて報告することを命じます。
前述の史実の通り、『ムジナモの花』によって、万太郎の名は世界に轟くことになるのかもしれません。
※詳しい内容が分かり次第、追記させていただきます。
【らんまん図鑑】18週ヒメスミレ
らんまん18週の花の名【ヒメスミレ】

らんまん18週ヒメスミレ|特徴
ヒメスミレ(姫菫、学名:Viola inconspicua Blume subsp. nagasakiensis)はスミレ科スミレ属の多年草。
その名の通りスミレの仲間ですが、花の大きさは一般的なスミレより小さく、直径1cmほどで、毎年4月から5月にかけて紫色の花を咲かせます。
本州から九州にかけて分布していて、日当たりが悪くてやや湿り気のある場所を好みます。
庭の隅や木陰・石垣のすき間などに見つかることが多く、都会ではアスファルトのひび割れから生えているのを見かけたりします。
らんまん18週ヒメスミレ|花言葉
スミレの花言葉は「謙虚」「誠実」「小さな幸せ」などです。
ヒメスミレの場合は、さらに「一途」が加わります。
中世ヨーロッパでは、男性が理想とする女性の三大要素をバラ、ユリそしてスミレの3種類の花で表したそうですが、スミレはそのなかでも「慎ましやかさ」や「ひたむきさ」を象徴していたと言われています。
らんまん18週ヒメスミレ|エピソード
スミレは昔から世界のさまざまな地域で親しまれていますが、日本においても同様です。
スミレという花の名前は、昔の大工さんが使った「墨入れ(すみいれ)」に由来しているのだとか。
墨入れの形とスミレの花の形が似ていたためといわれています。
松尾芭蕉や夏目漱石がスミレについて俳句を詠んだこともありました。
スミレは俳句では春の季語で、もっと時代をさかのぼってみると、あの万葉集にもスミレはよく取り上げられています。
日本では、スミレのことを「相撲取草(すもうとりぐさ)」や「相撲取花(すもうとりばな)」と呼ぶこともあります。
実は昔の子どもはスミレ同士を絡ませて引っ張る「花相撲」で遊んでいたのですね。
一方西洋においても、スミレは古代ギリシャ・ローマ時代から、しばしば神話に登場してきました。
例えば、太陽神アポロンがイアという人間の女性に恋をしましたが、彼女には婚約者がいたためアポロンの求婚を断りました。
するとアポロンはイアをスミレに変えてしまいました。
あるいは、愛の神ヴィーナスが息子のキューピッドと散歩をしているとき、乙女たちが踊っているのに遭遇。
ヴィーナスは息子に「私と彼女達とどちらが美しい?」と尋ねると、キューピッドは「乙女達」と答えたのだとか。
このためヴィーナスは怒り、乙女達の顔を紫色になるまでボコボコに叩き、哀れに思ったキューピッドは彼女達をスミレに変えたのだそうです。
以上のとおり、スミレは昔から洋の東西で親しまれてきたことがわかります。
しかしスミレを愛らしいもの・風流なものととらえた日本と、生々しい恋愛や嫉妬の感情につなげた西洋では、文化の背景の違いが垣間見えて興味深いですね。
【らんまん図鑑】19週ヤッコソウ
らんまん19週の花の名【ヤッコソウ】

らんまん19週ヤッコソウ|特徴
ヤッコソウ(奴草、学名:Mitrastemma yamamotoi Makino)は、光合成で成長に必要な養分を作り出す代わりに、シイノキなどの植物の根に寄生して養分をもらう寄生植物。
光合成を全く行わないので全体が緑色でなくて乳白色をしており、10月末から11月頃に白い花が咲きます。
全長は10cmに満たない1年草で、日本では四国や九州、沖縄に分布しており、徳島県が分布の北限です。
らんまん19週ヤッコソウ|花言葉
ヤッコソウの花言葉は存在しない、というのが通説になっています。
しかしその一方で、ヤッコソウの花言葉として「静かな力強さ」が示される場合もあります。
ヤッコソウの花言葉には複数の意見があるようです。
ヤッコソウはそれだけ珍しい植物で、花言葉に関しても定説が定まっていないようです。
らんまん19週ヤッコソウ|エピソード
ヤッコソウは高知県で発見され、らんまんのモデル・植物学者の牧野富太郎により命名されました。
牧野博士がなぜ「ヤッコ」と名付けたかというと、花の様子が大名行列の「奴(ヤッコ)」に似ていたからだそうです。
もともと「奴」は「しもべ」の意味で、武家に働く奉公人のうち最も低い身分の者たちを蔑むときの呼び方でした。
「奴」と呼ばれる者たちの中には「槍持奴」と呼ばれる人々がいて、大名行列の際には先頭に立ち半纏を着て、槍や衣類などの日用品を箱に入れて棒を通した「挟み箱」といわれる道具を運ぶ役目を担っていました。
槍持奴の多くは独特のスタイルで、髪を撥鬢(ばちびん、頭の左右の側面を三味線のバチの形に剃り込んだヘアスタイル)にして、鎌髭(かまひげ、鼻の下から左右へ鎌をさかさまにしたような形にはね上げたひげ)を生やし、季節に関係なく冬でも袷(あわせ)1枚というスタイルを通していたのです。
その姿がユニークだったので、正月に上げる凧に描かれることも多かったのだとか。
奴凧(やっこだこ)と聞けばピンと来る人も多いのではないでしょうか。
いずれにしても、シイノキの根本に寄生する、小さくて真っ白な植物に、大名行列の「奴」の名前をつける牧野博士のネーミングセンスもなかなかのものですね。
【らんまん図鑑】20週キレンゲショウマ
らんまん20週の花の名【キレンゲショウマ】

らんまん20週キレンゲショウマ|特徴
キレンゲショウマ(黄蓮華升麻、学名:Kirengeshoma palmata)は日本原産で、近畿から九州の山林内に生息する多年草。
希少な高山植物で、草丈は大きいもので120cmほどになります。
葉の長さは20cmほどで円形、手のひらのような割れ目があります。
毎年8月ごろになると、葉の大きさに比べるとずいぶん小さい2cmほどの黄色い下向きの花を咲かせます。
らんまん20週キレンゲショウマ|花言葉
キレンゲショウマの花言葉は「幸せを得る」です。
キレンゲショウマの花の黄色は黄金色を連想させ、明るさや幸せのイメージが見えてきます。
これに手のひらを連想させるキレンゲショウマの葉が加わると文字通り「幸せをつかみ取る」という意味につながり、花言葉の「幸せを得る」が実現することになりますね。
いずれにしても、キレンゲショウマの花が群生している様子は、見ているだけで幸せになってしまいそうですね。
らんまん20週キレンゲショウマ|エピソード
キレンゲショウマという名前は、東京大学の初代植物学教授だった矢田部良吉博士(らんまん田邊教授のモデル)が名付けたものです。
公式には1888年(明治21年)8月に矢田部博士が採集した花の標本と、同じ場所で1890年(明治23年)10月に吉永虎馬氏が採集した果実の標本に基づいて公に発表されました。
ただし1888年の発見も実は吉永虎馬氏によるもので、命名者の矢田部博士のところへは、吉永氏が鑑定依頼のため持ち込んだという異説もあります。
そんなキレンゲショウマは、徳島県の霊峰・剣山を舞台にした宮尾登美子の長編小説『天涯の花』(1998年発表)に登場して、よく知られるようになりました。
主人公は養護施設を出て剣山にある神社の神官の養女となって、巫女として働く少女、珠子です。
珠子はこの剣山に誇り高く咲くキレンゲンショウマを見ながら「私はこの花に出会うためにこの山に来たのかもしれない」と感じ、その美しい環境の中で、まっすぐに成長していきます。
またキレンゲショウマは、単なる物語の背景としてだけでなく、珠子の人生を左右する大事件の伏線としても登場します。
『天涯の花』は小説として出版されただけでなく、テレビドラマ化されたり、舞台演劇にもなったりしていますので機会があればぜひご覧ください。
【らんまん図鑑】21週ノジギク
らんまん21週の花の名【ノジギク】

らんまん21週ノジギク|特徴
ノジギク(野路菊、学名:Chrysanthemum japonense)は、キク科キク属の多年生植物で、日本固有種。
草丈は50cmくらいで枝分かれをしながら群落を作り、風通しのよい所を好み、強い海風が吹きつけるような海岸沿いによく生えています。
本州の西部から四国、瀬戸内海、九州の太平洋沿いの傾斜地に自生している野菊の一種です。
毎年10月下旬から11月ごろに、直径3~5㎝の素朴で白い花を咲かせます。
花の真中の部分は黄色で、葉は丸みを帯びた手のひらの形をしています。
らんまん21週ノジギク|花言葉
ノジギクの花言葉は「真実」「高潔」「高貴」です。
ノジギクは素朴な野菊の一種であるため、少し意外ですよね。
しかし白一色で飾り気のないその姿は、「本物の高潔」「本物の高貴」を表しているともいえます。
ありのままの素朴な自分をさらけ出す様子は、まさに「真実」そのもの美しい姿といえますね。
らんまん21週ノジギク|エピソード
ノジギクは1884年(明治17年)11月に、植物学者・牧野富太郎が、高知県吾川郡吾川村川口の仁淀川沿いの道端で発見し命名しました。
その後、牧野博士は兵庫県姫路市の大塩・的形地域を調査して、そこが「日本一のノジギクの群生地」であると知り大喜びしたのだとか。
牧野博士が大群落を発見した兵庫県姫路周辺は、ノジギクの分布密度が最も高いそうです。
それだけでなく、東の六甲山系にもノジギクの群落は見つかっています。
調査の結果、ノジギクの生育する東限は兵庫県神戸市の岡本のあたりで、北限は同じく兵庫県神戸市の有馬温泉のあたりであることがわかりました。
兵庫県にはノジギクの群生地が多いため、兵庫県では1954年(昭和29年)にノジギクを県の花に決定しました。
なお、兵庫県と広島県では見かけるのにその中間にある岡山県では、ノジギクを見ることはほとんどありません。
岡山県では絶滅危惧Ⅰ類に指定されていて、なぜそのような現象が起こったのか現在でも謎のままです。
【らんまん図鑑】22週オーギョーチ
らんまん22週の花の名【オーギョーチ】

らんまん22週オーギョーチ|特徴
オーギョーチ(愛玉子、別名:アイギョクシ、カンテンイタビ、学名:Ficus pumila L. var. awkeotsang (Makino) Corner)は、クワ科イチジク属のつる性植物です。
オーギョーチは台湾での呼び方で、日本ではアイギョクシ、カンテンイタビなどと呼ばれるのが普通です。
台湾固有の植物で、台湾では中央山地の山間地に自生しています。
種子から寒天状のデザートができるので、そのために栽培される場合もあります。
らんまん22週オーギョーチ|花言葉
オーギョーチの花言葉は見当たりません。
ちなみに、オーギョーチは観葉植物として人気のあるフィカス・プミラ(オオイタビ)の変種ひとつで、フィカス・プミラの花言葉は「あなたは私を勇気づける」「知識」です。
オーギョーチそのものを手に入れることは難しくても、近縁のフィカス・プミラの鉢植えを手に入れの良いアイデアといえますね。
らんまん22週オーギョーチ|エピソード
オーギョーチという呼び名は、日本では植物の名前としてよりも、台湾の夏のデザートとして知られています。
オーギョーチの果実を裏返しして中の種子を乾燥させて、水の中で揉み出すと、水がとろみを帯びてゼリー状になります。
このゼリーには味がないので、レモンシロップなどをかけて味を付けて食べます。
この変わった果実がオーギョーチと呼ばれるようになった由来は、台湾通史の「農業志」に記載されています。
種を水の中で揉み出すと水が固まる性質を見つけた人が、娘の名前「愛玉」にちなんで「愛玉子」と名付けたのだとか。
また楊貴妃の好物のひとつであったといわれています。
台湾では(もしかしたら中国大陸でも)昔から、庶民から高貴な人までオーギョーチを食べて夏を乗り切ったのかもしれませんね。
オーギョーチの水を「固める」成分はペクチンです。
オーギョーチの種にはペクチンが豊富に含まれていて、腸内環境を整えてくれたり、腎臓機能をアップする効果があったりするので、美容と健康に有効です。
昔から知られていたオーギョーチを、新種の植物として世界に紹介したのは、らんまんのモデルで植物学者の牧野富太郎です。
このことは、オーギョーチの学名に「Ficus pumila L. var. awkeotsang (Makino) Corner」と「牧野(Makino)」の名前が加えられていることからわかります。
牧野博士、1896年(明治29年)10月に東京大学の植物調査団として台湾入り。
約2カ月間にわたって、台湾を縦断して植物の調査や採集する中でオーギョーチを発見し、新種だと確認しています。
【らんまん図鑑】23週ヤマモモ
らんまん23週の花の名【ヤマモモ】

らんまん23週ヤマモモ|特徴
らんまん23週の花の名『ヤマモモ(山桃)』(学名: Morella rubra)は、中国南部から台湾・フィリピン・朝鮮半島南部・日本では関東より西を原産とするヤマモモ科ヤマモモ属の常緑樹です。
ヤマモモの木には雄木と雌木があり、雌木には、初夏のころ直径1cmから2cmくらいのルビー色の果実がなります。
ただしヤマモモの実は、果物屋さん等でのおなじみの「桃」とはまったく関係はありません。
新鮮な生のヤマモモの実は美味しいですが、朝収穫すると昼にはもう傷んでしまうほどで、煮物・ジャム・砂糖漬けなどに加工することが一般的です。
らんまん23週ヤマモモ|花言葉
ヤマモモの花言葉は、地味だけどひたむきな雰囲気を感じさせる「ただひとりを愛する」「一途」「教訓」の3つです。
そんなヤマモモの木には、3~4月ごろに小さく目立たない花が咲きます。
雌雄異株のため雄木と雌木の両方が生えていないと実がなりません。
雄木に咲く雄花が花粉を飛ばし、雌木に咲く雌花が受粉して実を付けるのです。
ただヤマモモの雄花は遠くからでも花粉を飛ばすので、雌花だけで果実を実らせたようにみえることもしばしばです。
らんまん23週ヤマモモ|エピソード
ヤマモモは、四国の人々にとって特別な意味を持っているのかもしれません。
高知県の県花であると同時に、徳島県の県木であると定められています。
ヤマモモが高知県の県花であることについては、次のような逸話が残っています。
全国の県それぞれに県花を定めることになった1954年、【らんまん】のモデルで高知県出身の植物学者・牧野富太郎博士はその選定委員会の委員長をしており、高知県の県花にヤマモモを定めました。
もっとも、最初に高知県が提案したのはノジギクだったのですが、県の花は北から順番に決めており、ノジギクは既に兵庫県の県花と決定した後でした。
そのため、高知県の県花候補が宙に浮く形になってしまいました。
困った中で「牧野先生、ヤマモモはどうですか?」という声が上がり、牧野博士が「それでよいだろう」と答えてヤマモモに決まったとされています。
牧野博士は後に、故郷の知人へ書いたハガキの中に、「土佐(高知)の県花はヤマモモと決まったようですが、それは適当です。でもこれは故郷の花では無くて故郷の果実だ・・・」といった趣旨の言い訳めいた一文を書いています。
もっとも牧野博士自身にとってもヤマモモは特別な存在だったらしく、自身が手掛けた植物図鑑の表紙にヤマモモの絵を描いたりしています。
また、最晩年はヤマモモの実の「香りに恋」をしたりしていたとも伝えられています。
【らんまん図鑑】24週ツチトリモチ
らんまん24週の花の名【ツチトリモチ】

出典:https://trippers.info/ 様
らんまん24週の花ツチトリモチ|特徴

*生育地の一つ「赤石山」山道
らんまん24週の花の名『ツチトリモチ(土鳥黐)』(学名:Balanophora japonica)は、ツチトリモチ科ツチトリモチ属の寄生植物です。
日本固有種で、紀伊半島、四国、九州、南西諸島の一部など、温暖な場所の森林内で見かけられます。
ただ、それぞれの生育地では絶滅危惧種・準絶滅危惧種に指定されてしまいました。
ツチトリモチの宿主は、ハイノキ属のハイノキやミミズバイ、クロキなどで、栄養分は宿主から摂取するため光合成は行いません。

*中央・ハイノキ
そのため緑色の部分は全く存在せず、一見真っ赤なキノコのように見えます。
高さは6cmから12cmほど、開花時期は10月から11月です。
らんまん24週の花ツチトリモチ|花言葉
ツチトリモチの花言葉は見当たりません。
当然ながら一般的な草花とは異なる『寄生植物』のため花言葉とは遠い存在のイメージですよね。

発見されて間もない花や、野草の多くにも当てはまるのですが、花言葉を持たない植物も多数存在しています。
ツチトリモチも野草のひとつですが、花がキノコにとてもよく似ているため、キノコと間違えて花のイメージで見られなかったのかもしれないですね。
らんまん24週の花ツチトリモチ|エピソード

ツチトリモチ(土鳥黐)という和名は、鳥を捕まえるときに使った鳥黐(とりもち)に由来しています。
鳥もちの作り方はいろいろありますが、ツチトリモチの根茎(イモのような塊)を取り出して、ネバネバするまで叩き続けるという方法があります。

このネバネバした粘着物を木の枝などに塗り付けてオトリや鳥笛を使って鳥をおびき寄せると、小鳥がそこに止まって足が離れなくなり捕まえることができるといいます。
また、長いさおの先に鳥もちをつけて追いかける方法もよく知られる方法ですね。
ただし現在は、鳥もちを使った猟は『鳥獣保護法』によって禁止されています。
このキノコのような外観のツチトリモチは、【らんまん】のモデルである植物学者・牧野富太郎博士にもゆかりがあります。

ツチトリモチの仲間であるキイレツチトリモチは、1910年(明治43年)に鹿児島県揖宿郡喜入(キイレ)村で小学校教諭の山口靜吾氏が採集した標本をもとに、牧野博士が植物学雑誌でその地名から名前を付け発表しました。
キイレツチトリモチはツチトリモチとは異なって、全体が黄色または淡い黄褐色です。
またキイレツチトリモチは海岸近くの低地林に生えることや宿主がトベラやネズミモチなどの根に寄生することなど、ツチトリモチとは異なる特徴がいくつかあるようです。
【らんまん図鑑】25週ムラサキカタバミ
らんまん25週の花の名【ムラサキカタバミ】

らんまん25週の花ムラサキカタバミ|特徴
らんまん25週の花の名『ムラサキカタバミ(紫片喰または紫酢漿草)』(学名:Oxalis corymbosa)は、カタバミ科カタバミ属の多年草です。
原産地は南アメリカですが、日本でも本州から沖縄まで広く分布する、非常に繁殖力の強い帰化植物です。
背丈は30cmほどで、クローバーに似たハート型の花が特徴です。
春から初夏の間、ピンクがかった紫色で2cm弱の小さく美しい花を咲かせます。
らんまん25週の花ムラサキカタバミ|花言葉

ムラサキカタバミの花言葉は「心の輝き」「喜び」です。
「心の輝き」は、その昔、カタバミの葉を真鍮(しんちゅう)製の鏡や祭具を磨くのに使ったことに由来し、「心を磨く」という意味から表しています。
カタバミの葉には『シュウ酸』という酸性の化学物質が多く含まれているため、真鍮のサビ落としに役立ったのだとか。
「喜び」は、カタバミの花がキリスト教の復活祭(3月末から4月末)の頃に花が咲くことに由来しています。そのため海外ではカタバミの花は「ハレルヤ」と呼ばれ、それを日本では「喜び」と表現したようです。
らんまん25週の花ムラサキカタバミ|エピソード

ムラサキカタバミは、江戸末期に観賞目的で輸入されました。
それから昭和中期までは珍しい植物として栽培されていましたが、やがて野生化。
現在は雑草として扱われるほど日本中に広がっています。
そんなムラサキカタバミは、環境省から『要注意外来植物』として指定されています。
この種はとても繁殖力が強く、生態系のバランスを破壊する恐れがあるからです。
紫色の小さな花は、はかない美しさも感じられますが、実はとてもタフな植物。
コンクリートのすき間からも平気で生えてくる強さを持っています。

なお、日本の気候では種が結実することはありません。
その代わり、鱗茎と呼ばれる地下茎で繁殖し根を地中深くまで潜り込ませ、栄養を効率的に吸収するなど強力な繁殖力を持っています。
一度生えるとなかなか駆除することができず、うっかり見過ごしてしまうと、駆除に大変な労力が必要となります。
完全な駆除は、素人には不可能かもしれません。
それでもムラサキカタバミは、とても魅力的です。
もともと観賞用として日本に入った植物で、オキザリス等の名前でいくつもの仲間が園芸用に使われています。

ムラサキカタバミを楽しみたいのなら、際限なく繁殖してしまうのを避けるため、『地植え』は止め『鉢植え』にして楽しむことをお勧めします。
日当たりと水はけの良い環境を好む育てやすい植物で、多くは耐寒性もあり、寒冷地でなければ屋外で越冬できます。
その一方、南アメリカ原産にしては、意外にも夏のギラギラする直射日光は苦手なんだそうですよ。
【らんまん図鑑】26週スエコザサ
らんまん26週の花の名【スエコザサ】

らんまん26週の花スエコザサ|特徴
らんまん26週の花の名前『スエコザサ(寿衛子笹)』学名:Sasaella ramosa var. suwekoana)は、イネ科アズマザサ属の多年草で、東笹(あずまざさ)の変種です。
日本の宮城県と岩手県南部に自生していて、葉の片方が裏に向かって巻いているのが特徴です。
高さは1~2mありますが、直径は4~6mmと細く、節の間の長さが7~15㎝あります。
寒さに比較的強いので、寒冷地の庭園では垣根などに利用されることがあります。
【らんまん】のモデルで植物学者・牧野富太郎博士が1927年(昭和2年)に仙台市で発見。
そのころ闘病中の寿衛子夫人を偲んで名付けられたことで有名です。(寿衛子夫人・昭和3年逝去)
らんまん26週の花スエコザサ|花言葉

出典:)https://www.flower-db.com/
『スエコザサ』自体の花言葉は不明です。
植物学者・牧野博士が亡き夫人を偲んで名付けたというエピソードだけで十分で、スエコザサ自体の花言葉を作ろうとした人が誰もいなかったのではないかと言われています。
一方、一般的な『笹』の花言葉は「ささやかな幸せ」です。
笹はめでたい松竹梅のうち「竹」の代用品として使われることがあります。
竹より高さが低いので、「幸せ」に「ささやか」が加わった「ささやかな幸せ」という花言葉が付いたと言われています。
ちなみに、笹や竹が花を付けるのは60~120年に1回というエピソードも、よく知られていることですよね。
らんまん26週の花スエコザサ|エピソード

【らんまん】でも描かれている通り、牧野博士の研究生活を物心両面で支え続けた寿衛子夫人は、博士にとっては特別な存在でした。
東京に植物学研究の大志を抱いて出てきた牧野博士が、ドラマ同様に行きつけの『お菓子屋の看板娘』の寿衛子さんを見初めたのが、お二人の出会いのきっかけです。
恋愛結婚だったからといっても、二人の生活はお菓子のように甘い幸せだったかといえば、それは困難な道のりでした。

牧野博士は多額の費用を研究に使うため、寿衛子夫人にはその金策や借金取りに追われる生活が待っていました。
しかも牧野夫妻の間には13人もの子供が次々に生まれ(うち6人は夭折)、寿衛子夫人は子供たちの世話や一人前に育て上げる教育のため、とても苦労をしたようです。
しかし、寿衛子夫人は牧野博士の夢を自分の夢として、家族のため、そして博士が自由に研究を続けることができるようにと全力でサポートをしました。
それらの苦労が実り、牧野博士は1927年(昭和2年)に理学博士を取得。

そして自宅も完成していよいよこれからという時に、寿衛子夫人は病に倒れたのです。
スエコザサは、寿衛子夫人を深く愛し続けた牧野博士の特別な思いが込められた命名でした。
【らんまん図鑑】毎週の花の名前|その姿や花言葉とドラマの関係が深い!|まとめ
【らんまん図鑑】は、NHK朝ドラ『らんまん』の毎週の副題の花の名について花言葉やエピソード、ドラマとの関係などをご紹介しています。
最愛の母・ヒサとの思い出が詰まった『バイカオウレン』をはじめ、副題の今週の花たちが物語に深みを与えています。
なお、それらの植物は、主人公・万太郎のモデルとなった植物学者・牧野富太郎博士に縁の深いものばかりです。
諸説ありますが、牧野博士は1500以上の新種草花に学名をつけ、約40万点にものぼる標本を残したとされています。
らんまん最終回の26週まで、波乱万丈の物語を演出する草花に注目です~♬

